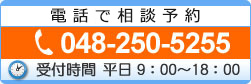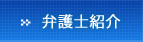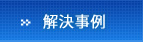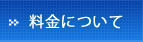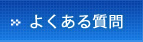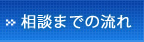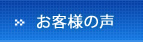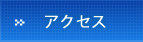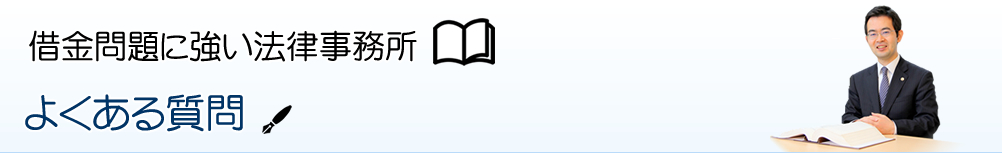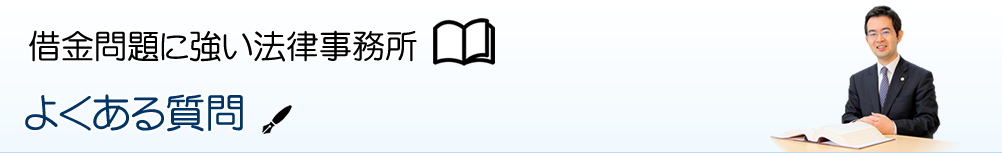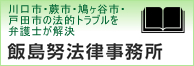※ご覧になりたい項目をクリックしてください。
自己破産について
Q 自己破産中にできなくなる資格・職種を教えてください
各種の法令には、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」は特定の資格を有しないとされ、自己破産手続中に特定の資格を失うこと(欠格事由)が定められています。
なお、破産による資格制限は、破産手続開始から「復権」するまでの数ヶ月から半年程度の期間に限られます(通常の場合)。「免責許可決定」が確定すれば、復権しての制限はなくなり、再びその資格で仕事をすることができます(破産法255条1項1号)。
以下に代表的な資格制限を挙げます。
1. 士業
・弁護士 (弁護士法7条)
・司法書士 (司法書士法5条)
・税理士 (税理士法4条)
・公認会計士 (公認会計士法4条)
・行政書士 (行政書士法2条の2)
・社会保険労務士 (社会保険労務士法5条)
・弁理士 (弁理士法8条)
・土地家屋調査士 (土地家屋調査士法5条)
・不動産鑑定士 (不動産の鑑定評価に関する法律16条)
・宅地建物取引士(宅地建物取引業法 18条)
・通関士 (通関業法6条)
2. 金融・保険・不動産関連業
・貸金業者 (貸金業法6条)
・生命保険募集人・損害保険代理店 (保険業法279条)
・証券外務員 (金融商品取引法29条の4)
・質屋 (質屋営業法3条)
・古物商 (古物営業法4条)
・建設業者 (建設業法8条)
3. 警備業
・警備員、警備業者 (警備業法3条、14条1項2項)
4. 公的な役職・委員など
・公証人 (公証人法14条)
・人事院の人事官 (国家公務員法5条)
・公正取引委員会の委員 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律31条)
・教育委員会の委員 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律4条)
・都道府県公安委員会の委員 (警察法39条)
・固定資産評価員 (地方税法407条)
5. その他
・後見人、保佐人、補助人(民法847条、876条の2、876条の7)
・遺言執行者 (1009条)
・特定非営利活動法人(NPO法人)の役員 (特定非営利活動促進法20条)
・商工会議所の役員 (商工会議所法35条)
・調教師、騎手 (競馬法施行規則22条1項)
・廃棄物処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律7条)
・風俗営業の管理者 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律24条)
6. 会社の役員(取締役、監査役など)
「欠格事由」とは異なりますが、破産手続が開始されると、会社との委任契約が終了するため、法律上当然に退任となります(民法653条)。ただし、株主総会の決議で再任されれば、再び役員に就任することが可能です。
※上記は代表的なものであり、すべてを網羅しているわけではありません。また、法律の改正により条文番号が変更される可能性もありますので、最新の情報や詳細は、専門家にご確認ください。
Q 免責不許可になった場合、どうなりますか?
免責不許可決定は、裁判所が、自己破産を申し立てた人(破産者)に対し、債務の支払義務を免除(免責)しないと判断する決定のことです。
1 免責不許可決定が確定すると、具体的には以下のような状況になります。
a. 借金の返済義務が残る
自己破産申立ての最大の目的である「債務の免除」が受けられないため、すべての債務がそのまま残ります。
b.債権者からの督促・差し押さえが再開される
弁護士からの受任通知または破産手続開始によって停止していた、債権者からの電話や手紙による督促、給与差押えやその他の財産の差押えなどが再開される可能性があり ます。
c.「破産者」である事実が残る
一部の資格や職業に就けない資格制限が残ります。資格制限は、復権が得られるまで続きます。
2 免責不許可決定後の対処法
a. 即時抗告
免責不許可決定に不服がある場合、破産者が免責不許可決定書を受け取ってから1週間以内に即時抗告をすることができます。ただし、決定を覆すためには新たな証拠を示す など、説得力のある主張が必要です。
b. 個人再生申立
個人再生は、借金を大幅に減額し、原則3年~5年間で分割返済していく手続きです。自己破産では免責不許可事由となるギャンブルや浪費が原因の借金であっても、個人再生であれば再生計画が認可される可能性があります。
c. 任意整理
任意整理は、弁護士が各債権者と個別に交渉し、将来利息のカットや分割返済を合意する手続きです。破産手続の中である程度財産状況が明らかになっているため、債権者としても、現実的な返済計画であれば交渉に応じてくれる可能性があります。
Q 「引っ越し」「旅行」「郵便物」の制限について
「引っ越し」「旅行」「郵便物」についての制限は、「管財事件」になった場合に適用されます。手続きが比較的シンプルな「同時廃止事件」の場合はこれらの制限はありません。
1. 「引っ越し」「旅行」の制限
管財事件になると、破産手続きが終了するまでの間、裁判所の許可なく居住地を離れること(引っ越しや長期の旅行・出張など)ができなくなります。
◯これは、破産管財人が財産の調査や換価を行うにあたり、いつでもご本人と連絡が取れる状態にしておくためです。また、財産を隠したり、手続きから逃亡したりするのを防ぐ目的もあります。
◯また、「一切どこにも行けない」というわけではありません。仕事の出張、冠婚葬祭、帰省など、正当な理由があれば、破産管財人に相談し、事前に裁判所の許可を得ることで可能です。無断で行うことが問題となるため、予定がある場合は必ず事前に報告・相談をしましょう。日帰りの外出など、宿泊を伴わない短期の移動であれば、通常は許可は不要です。
2. 郵便物の制限
管財事件では、破産手続き中に限り(破産手続開始決定から破産手続終結までの間)、ご本人宛ての郵便物(信書)が、すべて破産管財人の弁護士事務所へ転送されます。
◯これは、申告していない財産や債権者を発見するための重要な調査の一環です。例えば、銀行などの金融機関からの通知や、申告漏れの債権者からの督促状などを確認し、手続きに正確に反映させる目的があります。
◯破産管財人は、郵便物の中身を確認して破産手続きに関係ないと判断した郵便物(家族や友人からの個人的な手紙など)は、ご本人へ返却します。あくまで調査に必要なものだけをチェックするものであり、この郵便物の転送は破産手続きが終了すれば解除されます。
3.まとめ
破産手続き中の「引っ越し」「旅行」「郵便物」に関する制限は、「管財事件」において、手続き公正かつ円滑に進めるために設けられたルールです。正しく理解し、破産管財人としっかりコミュニケーションを取っていれば、過度に恐れる必要はありません。
Q 日本学生支援機構の奨学金は自己破産の対象になりますか?
日本学生支援機構の奨学金も、破産手続の対象となり、免責許可決定が得られれば、支払義務が無くなります。
ただし、連帯保証人や保証人がいる場合、日本学生支援機構から一括請求が行きますので、注意が必要です。
Q 医療ローン(美容ローン)も自己破産の対象になりますか?
医療ローン(美容ローン)による債権も、破産手続の対象となり、免責許可決定が得られれば、支払義務が無くなります。
Q 生活保護を受けていますが自己破産できますか?
生活保護を受けている方の債務整理手段としては、通常、自己破産一択となります。
生活保護費から借金を返済することは、通常は、役所が認めないからです。
Q 自己破産すると銀行口座を開設できなくなりますか?
過去に破産したことがある人であっても、普通は、新規に銀行口座を開設することは可能です。
すなわち、破産したことを理由に口座の新規開設を拒否されることは、普通は無いはずです。
Q 自己破産すると銀行口座が凍結されますか?
自己破産を弁護士に依頼したとしても、その銀行から借入れ(カードローン、住宅ローンなど)が無いのであれば、通常は口座が凍結されることはありません。
逆に、その銀行から借入れがあれば、弁護士が受任通知を送付した時点で、口座が凍結される(口座内のお金を出金できない状態にすること)ことが普通です。銀行としては、貸付金を回収するために、相殺(貸付金額の限度で口座内のお金を没収すること)をするからです。
Q メルペイやPaidyなどの後払い決済業者も自己破産の対象になりますか?
後払い決済業者の債権についても、破産手続きの対象となり、免責許可決定が得られれば、支払い義務が無くなります。
Q 自己破産手続中に携帯電話会社のキャリア決済を利用することはできますか?
携帯電話会社のキャリア決済(携帯料金支払いと合算して支払う決済サービス:auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い、ワイモバイルまとめて支払い、d払いなど)は、携帯電話会社に対する偏頗弁済となる可能性があるので、破産手続中は利用しないようにしてください。
Q 「免責調査型管財事件」とは何ですか?
ある程度財産がある方が自己破産を申し立てた場合、管財事件となり破産管財人が付くことになります。
一方、財産がほとんど無い方であっても、負債形成の主な原因が浪費やギャンブルであるなど明らかな免責不許可事由がある場合には、免責不許可事由や裁量免責が可能かを調査させるために、裁判所が破産管財人を選任することになります。
このケースを「免責調査型管財事件」といいます。「免責調査型管財事件」になることが想定される場合には、申立前の準備期間中に、弁護士費用に加えて、管財予納金20万円を積み立てておくことが必要となります。
Q 破産手続きに掛かる期間はどのくらいですか?
【同時廃止事件の場合】
破産申立てから約1ヶ月以内に裁判官面接があり、破産手続開始・手続廃止決定がなされます。その後2~3ヶ月後に、免責に関する決定がなされます。なお、裁判官面接は、上記のタイミングではなく、免責に関する決定の直前に行われる場合もあります。
【管財事件の場合】
破産申立ての後、破産管財人が選任され、約3~4ヶ月後に第1回債権者集会が指定されます。財産の換価・債権者への配当など、破産管財人による業務がすべて終了した後に、免責に関する決定がなされます。破産手続が終了するまでにかかる期間は、財産の性質(換価が容易かどうか)により大きく左右されます。
Q 2度目の破産申立て
過去に破産し免責許可決定を受けたことがある人が、その後再び借り入れをしてしまい返済不可能となり、2回目の破産申立てをするケースがあります。
このような場合、再び破産はできるのでしょうか。また、免責は許可されるのでしょうか。
まず、客観的に返済不能であれば、過去に破産したことがあっても、再び破産手続開始決定を得ることは可能です。
しかし、再び免責許可決定が得られるかというと、話は違ってきます。
すなわち、①前回の免責許可決定の確定から7年以内の申立てであれば免責不許可事由に該当するため、再度の免責許可決定をもらうのは通常は難しいと思われます。
また、②前回の免責許可決定から7年が経っているのであれば、法律上、免責不許可事由には該当しませんが、裁判所は免責許可・不許可の判断に慎重になるため、簡単にはいきません。
再び負債を抱えることになった経緯について詳細に裁判所に報告し、前回の反省をふまえ、今回の借入れが真にやむを得ないものだった、ということを裁判所に理解してもらうことが必要となります。
場合によっては、管財事件となり、破産管財人の家計指導や調査を受けるということもあります。
このように、2回目の破産免責は、1回目よりも難易度が上がるといえるでしょう。
Q 「同時廃止事件」とはなんですか?
破産手続開始と同時に破産手続が廃止(終了)される事件を「同時廃止事件」といいます。裁判所が「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」(破産法216条1項)に同時廃止決定がなされます。20万円以上の資産を持っていない人の場合、多くが同時廃止事件となります。破産手続きが開始と同時に終了してしまうので、債権者集会が開かれることはありませんし、郵便物が破産管財人に転送されたり、転居する場合等の裁判所の許可は必要ありません。破産申立事件のうち過半数が「同時廃止事件」として処理されているようです。
Q 「管財事件」とはなんですか?
破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任される破産事件を「管財事件」といいます。この場合、破産者は財産の管理処分権を失い、破産管財人が破産者の財産を換価(財産をお金に換えること)し、債権者に配当するだけの財源ができれば配当されることになります。また、破産者宛ての郵便物は破産管財人に転送され、破産者が転居する場合等には裁判所の許可が必要となります。
Q 破産管財事件と同時廃止事件の振分基準について
個人が破産申立をする場合には、次の1~6の場合には「破産管財事件」になり、その他の場合には「同時廃止事件」となります。なお、法人が破産申立をする場合には常に「破産管財事件」になります。 1.個人事業を営んでいる場合 2.法人の代表者である場合 3.免責不許可事由が疑われ、破産管財人による免責調査が必要である場合 4.評価額20万円以上の資産を持っている場合 5.20万円未満の資産しか持っていないが、破産申立ての前に重要な財産を処分したり偏頗弁済等をした場合 6.その他、破産管財人による調査が必要である場合
Q 破産管財人とは何ですか?
破産管財人とは、破産した人の財産を管理し、お金に換え(換価)、そのお金を債権者に配当するなどの事務を行います。破産手続開始決定と同時に選任され(通常は弁護士が選任されます)、裁判所の監督を受けます。このように、破産管財人が選任される破産手続きを「破産管財事件」といいます。
Q 差押禁止財産とは何ですか?
法律上差押えが禁止されている財産を、差押禁止財産といいます。 差押禁止財産については、破産手続きによっても処分されることはありません。 例えば、衣服、寝具、家具、生活保護受給権などは差押禁止財産です。 また、66万円以下の現金は差押禁止財産ですが、破産手続きにおいては、この範囲が99万円以下に拡大されています。 なお、民事執行法上の差押禁止財産(民事執行法131条)・差押禁止債権(同法152条)、特別法上の差押禁止財産(生活保護法58条、国民年金法24条など)があります。
Q 自由財産拡張とは何ですか?
破産法は、破産者の経済的再生の見地から、破産手続によっても処分されず破産者が自由に管理・処分できる財産=「本来的自由財産」を認めています。例えば、99万円以下の現金や、差押禁止財産(給料の一部、年金受給権等等)が「本来的自由財産」に該当します。 ただ、上記の「本来的自由財産」だけでは、破産者の経済的再生が困難である場合もあり得ます。そのような場合には、裁判所は、破産者の申立てを受け、自由財産の範囲を拡張する決定をすることができます。この制度を、「自由財産拡張」制度と言います。 なお、さいたま地方裁判所の運用では、預貯金・保険解約返戻金・自動車などの財産で、総額99万円(すべての財産の総額です)以下のケースでは、拡張を認めることが多いです。 「自由財産拡張」制度については、各地の裁判所によって運用が異なるので、詳しくは弁護士にご相談ください。
Q 自己破産の手続きの流れを教えてください。
■弁護士と面談・契約
■受任通知を発送
※受任通知により取立てが止まります
↓
■裁判所提出書類の準備
■貸金業者より取引履歴の開示
↓
■利息制限法による引き直し計算(制限利率を超える借入れの場合)
■債務額又は過払金額の確定
↓
■過払金がある場合は過払金を回収
↓
■裁判所に申立書を提出
【同時廃止の場合】
■破産手続開始・廃止決定
↓
■免責許可決定
【管財事件の場合】
■破産手続開始・破産管財人選任決定
↓
■破産管財人による財産の換価処分
■破産に至った経緯の調査
↓
■債権者集会(複数回開催されることもあります)
↓
■配当手続
↓
■破産手続集結
■免責許可決定
Q「免責不許可事由」とは何ですか?
1 裁判所が免責を許可しないケースは、「破産法」という法律で具体的に定められており、これを「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」といいます。ただし、免責不許可事由に該当する行為があったとしても、直ちに免責が不許可になるわけではありません。
2 免責不許可事由は、おおまかに言うと、『著しく不誠実な行為』や『破産制度を悪用するような行為』です。このような行為をした人に対してまで、借金をゼロにすることを認めるのは、債権者にとって酷であり、社会の公平にも反するという考えに基づいています。具体的には、以下のようなケースが定められています。
3 代表的な免責不許可事由は以下のとおりです。
A 財産を不当に減少させる行為(財産隠しなど)(破産法252条1項1号)
・財産を隠したり、誰かに譲渡したり、不当に安い価格で処分したりする行為など
・具体例:預金口座の存在を隠す、所有している自動車を友人名義に変える、など。
B 著しく不利益な条件での債務負担や、信用取引による財産の処分(破産法第252条1項2号)
・いわゆる「クレジットカードの現金化」が典型例です。商品を購入する意思がないのにクレジットカードで商品を購入し、それをすぐに安い値段で業者に買い取ってもらい現金を得る行為など。
C 特定の債権者にだけ返済する行為(偏頗弁済:へんぱべんさい)(破産法第252条1項3号)
・友人や親族、特定の金融機関など、一部の債権者にだけ優先して返済する行為です。破産手続では、全ての債権者を平等に扱わなければならないという原則(債権者平等の原則)に反するため、問題視されます。
D 浪費やギャンブルによって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したこと(破産法第252条1項4号)
・実務上、最も問題となりやすい免責不許可事由です。
・具体例:収入に見合わない高価な買い物を繰り返す、パチンコ・競馬・FXなどで多額の借金を作る、過度に高額な飲食を繰り返す、など。
・「どの程度から浪費になるか」は、その方の収入や資産状況、借金の総額などから総合的に判断されます。
E 返済できないとわかっていながら、それを隠してお金を借りる行為(詐術による信用取引)(破産法第252条1項5号)
・収入や他の借金の状況について嘘をついて信用させ、お金を借り入れた場合などです。破産申立ての直前に、多数の金融機関から借り入れを行うようなケースも、これに該当する可能性が疑われます。
F 裁判所や破産管財人への説明義務違反・虚偽説明・業務妨害(破産法第252条1項8号,9号)
・破産手続が開始すると、裁判所や破産管財人から、財産や借金の経緯等について説明を求められます。この調査に協力しなかったり、嘘の説明をしたりすると、そのこと自体が免責不許可事由となります。
G 過去7年以内に免責許可決定が確定したこと(破産法第252条1項10号イ)
・短期間のうちに何度も自己破産による免責を認めるのは妥当ではないという趣旨の規定です。
4 上記の免責不許可事由に該当する行為があったとしても、多くのケースでは最終的に免責が許可されています。これを「裁量免責(さいりょうめんせき)」(破産法第252条2項)といいます。これは、裁判所が、破産手続に至った経緯や、本人の反省の度合い、手続への協力姿勢など、あらゆる事情を考慮して、「免責を許可するのが相当である」と判断した場合に、裁判所の裁量によって免責を許可する制度です。
5 裁量免責が認められやすいと思われるケース
以下のような事情がある場合、免責不許可事由があったとしても、裁量免責が認められる可能性が高まります。例えば、借金の原因がギャンブルであったとしても、その事実を正直に申告し、ギャンブル依存から脱却しようと努力し、破産手続きに誠実に協力すれば、多くの場合で裁量免責が認められています。
◯ 免責不許可事由の程度が軽微である
例:浪費の金額が借金全体のごく一部である
◯ 破産手続に誠実に協力している。
例:裁判所や破産管財人からの質問に正直に答え、求められた資料をきちんと提出している
◯ 深く反省し、経済的な更生の意欲を示している
例:家計簿をつけるなどして生活態度を改め、二度と借金を繰り返さないという強い意思を示している。
◯ 破産管財人による調査に全面的に協力し、管財人から「免責を許可するのが相当」という意見が出されている。(管財事件の場合)
6 免責不許可になる可能性が高いケース
以下のような場合は、裁量免責も認められず、免責が不許可となる可能性が高まります。特に、財産隠しや虚偽の申告といった、破産制度の根幹を揺るがすような不誠実な行為に対しては、裁判所は厳しい判断をする傾向にあります。
◯ 免責不許可事由の内容が悪質かつ重大である。
例:財産を計画的に隠した
◯ 裁判所や破産管財人に嘘をついたり、調査に協力しないなど、態度が不誠実である。
◯ 免責不許可事由(浪費など)について反省の態度が見られない。
7 実務上は、免責不許可事由があるケースでも、「裁量免責」によって多くの方が救済されています。大事なことは、依頼した弁護士にすべて正直に話すことです。たとえ、ご自身で「これは浪費かもしれない」「友人にだけ返してしまった」といったご心配な点があったとしても、それを隠さずに弁護士にご相談ください。正直にお話しいただくことで、弁護士は、裁判所や破産管財人に対して、あなたの反省の意や更生の意欲を十分に伝え、裁量免責を得るための最善の方策を一緒に考えることができます。
⇒ 一覧に戻る